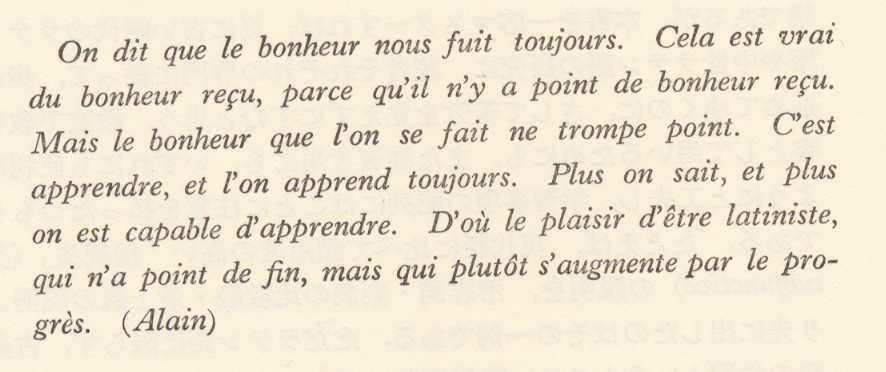|
|
|
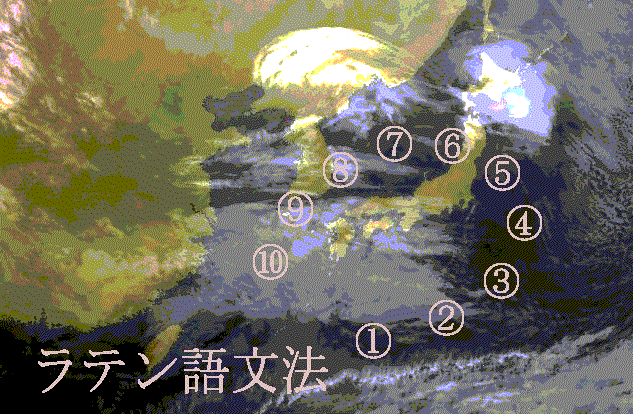
���Ǝ���ɂ���Ĥ���Ƃ��ACicero'�́A�L�P���[�ł��邪��V�Z���[�ɂȂ�����A�c�B�c�F���[�ɂȂ����肵�Ă���B�icf:cicerone�j
���m�Ȕ�����\������Ӗ��͂��܂�Ȃ��i�ƌ������ͤ���Ђ���������������݂��Ă���j�B
�@�@�@���߂ƃA�N�Z���g�y����z
�@A:�q���͎��̕ꉹ�ɂ��A���߂̋���-�Ŏ����Ƥno-va,
e-ro, re-po'-no', spe'-ro, a-mar
B:�q��������ԂƂ����߂͂��̊Ԃɂ���.
C:�@�ip,b,
t,d, c,g �j+ l�Ar �̌��т��͕�����Ȃ�.��̕ꉹ�ɂ����ƂɂȂ�.
�@�@�@la-cri-ma, fra'-tris, mem-brum,
ni-gro'tem-plum
D:
�������������ͤ�v�f�ɏ]���Đ邱�ƂɂȂ�B
�@�@�@ab-est, in-eo' �iab-, in-,
�͐ړ����j
�@�@�A�N�Z���g
�@A:�ꉹ�߂̌�͖��ɂ��Ȃ��A�O�u���Ȃǂ͖��A�N�Z���g�̏ꍇ�������B
�@B:�߂̌�͍ŏ��̌�ɃA�N�Z���g������B
�@�@�@�@rosa, faba, ama's, a'ra,
terra, adde
C:�O���߈ȏ�̌�́Apaenultima��������̂Ƃ�.�I��肩���ԖڂɃA�N�Z���g������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ʒu�ɂ���Ē����Fhoestus,
amantur, appello'
�Ōォ���Ԗڂ̕ꉹ��������Z���Ă��A
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�q������ȏ���ԂƂ��Along
by position��paenultima�ɃA�N�Z���g������.
�@D:vocaveris, philosophia, dominam�@�̂��Ƃ��A�Ōォ���Ԗڂ̕ꉹ��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Z���߂̏ꍇ�ͤantepaenultima�ɃA�N�Z���g������.
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�M���V����ł����A�E���e�B�}�ɃA�N�Z���g��������߂ł��邱�Ƃ͂Ȃ�.
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@antepaenultima
�@E:-que�i����сj, -ve(���邢��),
-ne(�[���H), �̂悤�Ȑڔ����i��ߎ��j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�̂悤�ȃA�N�Z���g�������Ȃ����̂����Ƃ����̑O��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���߂ɃA�N�Z���g������,rosaque,
terrave, ama'bone,
F:������ͤ�v�f�ɏ]���ăA�N�Z���g���^������.
trans-eo', in-ibit
�@ �� -nct, -gn, -ns, -nx,
�̒��O�̕ꉹ�ͤ�����ł���.
�@�@�@��2.�����̕ω�
�@�K�������ɂͤ�P�`4�܂ł̊��p�`������.
�@
�@�K�������̒����@���݁i�\���j
�@�@�@�@�@���@�ȉ��A�N�Z���g�L��,�����L���͌����p���Ȃ�.
�@��ꊈ�p
amare
�@�@�@�@�P��
�@�@�@�@1. (ego)
amo ����������
2. (tu) amas�@�@�N��������
3. (is) amat�@�@�ނ�������
�@�@�@�@����
1. (nos)�@�@amamus ��X��������
2. (vos) amatis�@�N������������
3. (ei) amant �ނ炪������
�@�@�@�@�@�@�@���@���̏ȗ��ɂ��Ăͤ�M���V����Ɠ�����.
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����ͤ�����@���݈�l�̔\���@amo�@�����o���ɂ��Ă���.
�@��p
�P��
1. moneo
2. mones
3. monet
�@�@�@�@����
1. monemus
2. monetis
3. monent
�@��O���p
�P��
1. rego
2. regis
3. regit
�@�@�@�@����
1. regimus
2. regitis
3. regunt
�@��l���p
�P��
1. audio
2. audis
3. audit
�@�@�@�@����
1. audimus
2. auditis
3. audiunt
���@���`�ͤ�p��Ƃقړ����ł��褁u���j�I���݁v
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ݐi�s�`�̈Ӗ��������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@canit (<cano,�V)�@He
sings, He is singing.
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���p�̌���T�`�W�Ŏ����Ă���.
����ω��݂̂�\�ɂ���ƈȉ��̂悤�ɂȂ�B
| �T | �U | �V | �W | |
| �P��1�l�� | -o | -eo | -o | -io |
| �@�@2 | -as | -es | -is | -is |
| �@�@3 | -at | -et | -it | -it |
| ����1�l�� | -amus | -emus | -imus | -imus |
| �@�@2�@ | -atis | -etis | -itis | -itis |
| �@�@3 | -ant | -ent | -unt | -iunt |
�@�@�@��3.�s�K�������́@esse,
prodesse, posse
�s��@����esse
�����@����
�@�@�@�@�P��1:sum
�i�킽�����j����B
2:es
3:est
�����P:sumus
2:estis
3:sunt
�@�s��@����prodesse
�����@����
�@�@�@�@�@�P��1:prosum �𗧂�
2:prod-es
3:prod-est
����1:prosumus
2:prodestia
3:prosunt
�@
�@�s��@����posse
�����@����
�P��1:possum
�E�E�ł���
2:potes
3:potest
����1:possumus
2:potestis
3:possunt
�@�@�@���S.non�ɂ���
�@�@�@non moneo.�@�@�@�@�@���͒������Ȃ�.
non potes regere.�@�@�N�͎x�z���邱�Ƃ��ł��Ȃ�.
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@possum�͉p��̂悤�ɕs��@�Ƌ��ɗp���邱�Ƃ��ł���.
non audire.�@�@�@�@�@�����Ȃ����Ɓi�����p�@�j�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ے肷��P��̑O�ɂ������ƍl���Ă����悢�B�@
�y��ɐg�ɂ����K���z�ȏ�̉���������o���B
�@�@�@���T.�����̑��`��ܕω��ɂ���
�@�����̕ω��ͤ�M���V����⤃h�C�c����C���[�W����悢�B
�܂��������
masculinum(m): vir�@�@�@�j
nauta�@�@���v
liber�@�@�{�@
sol�@�@�@���z
femininum(f): mulier�@�@��
filia�@�@ ��
mensa�@�@ ��
luna�@�@�@��
neutrum(n): bellum�@�@�푈
corpus�@�@��
otium �@�@��
mare�@�@�@�C
�@���ɂ��Ă�
singularis(sg)
pluralis(pl)
�ŁAdual�͂Ȃ��B
�@�@�i��
�@�@��i�@�Ċi�@���i�@�^�i�@�Ίi�@�D�i�@�n�i
�́A���ł���.
�@�@�@�@�����̑��ω� puella(f):����Ⴂ��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����ω��ȊO�́A��i�ƌĊi�������ɂȂ�̂Ť�ʂɎ����Ȃ�.
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�P���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����
��E�ā@�@ puell-a
puell-ae
�@��
puell-ae
puell-a'rum
�@�^
puell-ae
puell-i's
�@��
puell-am
puell-a's
�@�D�@
puell-a'
puell-i's
�̂��Ƃ��ł���B
���D�i�́A�`����A�̂悤�ɕ������Ӗ�����Ƃ���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�`�Łi�`���������āj�̂悤�Ȏ�i������킷�Ƃ��Ɏg�p�����.
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�n�i�́A����Ȗ����ɂ̂ݑ��݂��A�`�ɂ����āi�ꏊ�j�A�ƂȂ�A���p�\�ɓ���Ȃ��Ƃ�������.
casus nominativus
non, N
casus vocativus
voc, V
casus genitivus
gen, G�@�@�@�����ɂ́A���i����Ɛ����������.
casus dativus
dat, D
casus accusativus
acc, A
casus ablativus
abl, Ab �@�D�i
casus locativus
loc, L �@�@ �n�i
�̂悤�Ɏ���.
�@���Ƃ���
�@�@�@�@rosa, �@agricola, filia reginae Cormeliae �@�@�@dat.
����@�_�v��@�@���́@�����́@�R���l�[���A�Ɂ@(<do)�^����.
�_�v�椏����̖��̓o��(pl)���R���l�[���A�ɂ�������B
�ƌ������͂��o���オ�邱�ƂɂȂ�.
�@�@�ꏇ�͂��Ȃ莩�R�ł��邯��ǂऊT�ˈȉ��̂悤�ɂȂ�.
�@�@���\�\���̏C���\-�ԐږړI��\�\�����\�\�����B
�@�@filia nautae Corneliae rosas semper dat.
���v�̖��̓R���l�[���A�Ƀo���������^����B
�@�@ puella rosas amat.�@�o�����D���Ȃ̂͏����Ȃ̂��B
rosas puella amat.�@�������D���Ȃ̂̓o���Ȃ̂��B
amat rosas puella.�@�����̓o�����D���Ȃ̂��B
�@�@�@�@�E�E�E�E�E
�@�@�@���T.�����̑��ω�
�@�܂����ω�
�@�j�������@dominus�i��l�j�A puer�i���N�j�A liber�i�{�j
�P��@�@�@domin-us
puer
liber
�@�� �@�@ domin-e
puer
liber �Ċi�ɈقȂ�ω������̂͑��ω��j�������̂݁B
�@�� �@�@ domin-i
puer-i' libr-i'
�@�^ �@�@ domin-o'
puer-o' libr-o'
�@�� �@�@ domin-um
puer-um libr-um
�@�D�@�@ domin-o'
puer-o' libr-o'
����E�� domin-i
puer-i' libr-i'
�@��
domin-o'rum puer-o'rum
libr-o'rum
�@�^
domin-i's puer-i's
libr-i's
�@��
domin-o's puer-o's
libr-o's
�@�D
domin-i's puer-i's
libr-i's
�@���������@�@do'num �i�����j
�@�@�@�@�@�@�@�@�P�� ����
�@��E��
do'n-um do'n-a
�@�� do'n-i'
do'n-o'rum
�@�^ do'n-o'
do'n-i's
�@�� do'n-um
do'n-a
�@�D do'n-o'
do'n-i's
Revelation 22:21 gratia Domini nostri Iesu Christi cum omnibus
���ω��ɑ����閼���̂����A�P����i�� -us �ŏI�����̂́i�t�͂����ł͂Ȃ����j�w�ǒj���A
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ -um �o�I�����̂͂��ׂĂ������ł���B
�@���ω��j���т̂��� ius �ŏI����̂ͤ�P�����i�ɂ����� -ii' �ƌ����K���I�ȏI�����̂ق���
-i ���g����B
�@filius(���q)--> fi'l(i)i, ���� -ius �̌`�͌ŗL�����ɂ����������
Iu'lius --> Iu'li' �܂��P���Ċi���@fi'li-e �ł͂Ȃ�
fi'l-i' �ƂȂ邱�Ƃ�����.
Hora'tius --> Hora'ti'�B
�@�@�@���T.�`�e���̕ω�
�@�@���ω��E���ω��ɂ��āAbon-us,
-a, -um �i�悢�j�ɂ��Ă܂Ƃ�
���̕ω��ɑ�����`�e�������Ă݂�B
| �j | �� | �� | ||
| �P�� | �� | bonus | bona | bonum |
| �� | bone | bona | bonum | |
| �� | boni | bonae | boni' | |
| �^ | bono' | bonae | bono' | |
| �� | bonum | bonam | bonum | |
| �D | bono' | bona' | bono' | |
| ���� | ��E�� | boni | bonae | bona |
| �� | bono'rum | bona'rum | bono'rum | |
| �^ | boni's | boni's | boni's | |
| �� | bono's | bona's | bona | |
| �D | boni's | boni's | boni's |
�@�j�� ���ω��j������
dominus
�@�����@�@���ω���������
puella
�@�����@�@���ω���������
do'num
�Ȃǂ͓����ω�������B
�@
�@�������ͤ�`�e���Abonus �Ɠ����ω�������.
pri'm-us, -a, -um
secund-us, -a, -um
terti-us, -a, -um
quart-us, -a, -um
quint-us, -a, -um
sex-us -a, -um
septim-us, -a, -um
octa'v-us, -a, -um
no'n-us, -a, -um
decim-us, -a, -um
���ɤ���L�`�e���ł��邪��p��قǂɂ͗p������Ӗ��͋���.
�@ me-us, -a, -um�@�@�@�@����
tu-us, -a, -um�@�@�@�@�N��
su-us, -a, -um�@�@�@�@������
noster, -tra,-trum�@�@�@��������
vester, -tra,-um�@�@�@�@�N������
su-us, -a, -um�@�@�@�@���������́@�@�i����������L�������̂̐����i�Ɉ�v������j�B
�����i�̈�v�ɂ��Ă͎��̂Ƃ���ł���.�@�@sum�@�Ȃǂ̎�������p���āA�q��I�ɗp������ꍇ�������ł���.
puer miser�@�@�@�@�@�@�@�@�@����ȏ��N��
pulla bona�@�@�@�@�@�@�@�@�@�悫������
ami'ca mea est pulchra�@�@�@���̏��F�B�͔�����
sero'rum pigro'rum�@�@�@�@�@�ӑĂȓz�ꂽ����
�̂悤�ɂł���B
�@�`�e���ͤ���̂܂ܖ����Ƃ����p�����邱�Ƃ������B
bonus m�@�@�@�@�@�P�ǂȒj
bona f�@�@�@�@�@�P�ǂȏ�
bonum n�@�@�@�@�@�P�A�悫����
bona n,pl�@�@�@ ���Y
�@
�@���͂����̤ amicus �F�l�A�ͤ�{���@amo',�D�ӓI�Ȥ�Ƃ����`�e���ł����Ĥ�]���A�����`
ami'ca �́A���F�B���w��.
�@�@�@���U.�����̕ω��i�Q�j
�@�s�K������ sum �̒����@�ߋ�
sg. pl.
1: Eram
1: erA'mus
2: Era's
2: erA'tis
3: Erat
3: Erant
(capital�̓A�N�Z���g�̏��݂�����)
�@�ߋ��́A�p��̉ߋ��i�s�`�ɂ�₿����.�b�҂̈Ӑ}���W������Ă���ꍇ�̕\���ł����Ĥ�����E�����E�n���̊����������Ƃ��Ȃ��B
�@�����@�ߋ��i�\���j
�@servi' cibum et aquam carri's porta'bant.
�z�ꂽ���͐H���Ɛ����Ԃʼn^�т�����.
iamque rubesce'bat Auro'ra.
�@���債�ċł��g�݂����낤�Ƃ��Ă����B
�@�@��ꊈ�p amo' (������)�̉ߋ��A�\���E�����������
ama'bem
ama'ba'mus ama'bar
ama'ba'mur
ama'ba's
ama'ba'tis ama'ba'ris , -re ama'ba'mini'
ama'bar
ama'bant ama'ba'tur
ama'bantur
�ƂȂ�B�����̎����Ɋւ��Ăͤ
�����@�Ɂ@�@�@����
�@�@�@�@�@�@�@�ߋ�
�@�@�@�@�@�@�@����
�@�@�@�@�@�@�@����
�@�@�@�@�@�@�@�ߋ�����
�@�@�@�@�@�@�@��������
�ڑ��@�Ɂ@�@�@����
�@�@�@�@�@�@�@�ߋ�
�@�@�@�@�@�@�@����
�@�@�@�@�@�@�@�ߋ�����
���ߖ@�Ɂ@�@�@����
�@�@�@�@�@�@�@����
�s��@�Ɂ@�@�@����
�@�@�@�@�@�@�@����
�@�@�@�@�@�@�@����
�����Ɂ@�@�@�@����
�@�@�@�@�@�@�@�ߋ�
�@�@�@�@�@�@�@����
gerundium ��
�@�@�@�@�@�@�@�^
�@�@�@�@�@�@�@��
�@�@�@�@�@�@�@�D
gerundivum --
supinum �T
�@�@�@�@�@�@�@�U
�@�@�̂��ꂼ��ɑ��`�l���p�����ꂼ���̂悤�ɑ��݂���.
�@�@�@���V.�s�K������ sum �̕ω�(�����@����)
�@�T�@�@�@�@�@�@�U
ero'
erimus
eris
eritis
erit
erunt
�@�@�@���W.�O�u��
�@�@ad�@�Ίi�x�z to
�ɂقړ�����.
�@�@�@�@�@�@�@ad oppidum
���̂ق���
ad caelum�@�@�V�Ɍ�������
a' �q���̑O
ab�@�@�ꉹ�̑O
abs �ic , q, t �̑O�̑����j
�@�@�@�@�@���i�x�z�@�@�`����i����āj
puer ab oppido' venit ���N��������������B
ab alto' ad altum ������荂����
e' �q���̑O
�@�@ex �ꉹ�̑O
�@�@�@�@�@�D�i�x�z�@�@�i�`�̂Ȃ��j����i���Ƃցj
ex oppido' ������
e' caelo' �V����
de' �D�i�x�z�@�@�@of�@�ł��邪�A�`�ɂ��āA�`����idown
from�j
de' ami'citia' �F��ɂ���
de' facto'�@�@�@�@�����ɂ��āA������
in �Ίi�E�D�i�x�z
�@�@�@�@�@�Ίi�̏ꍇ�Fin , against �Ȃǂ��Ȃ�L���Ӗ������B
in oppidum ���Ɂy�̂Ȃ����z�ނ����āB
in multo's ���N�A���N�ɂ킽���āB
�@�@�@�@�@�D�i�̏ꍇ�F�Î~�I�� in , on
in oppido' ���̒��ɂ����āB
in populo' ���R�ƁB
cum �D�i�x�z�Fwith �ɑ�������B
�@�@�@�@�@�@�@�@cum gaudio' ��т������āB
puer cum ami'co' venit
���N���F�l�Ƌ��ɂ���Ă���B
�@�@�@���W.�s�K������
eo' ���s�����i�s��@���� i're�j�̕ω�(�����@�A���݁E�ߋ��E����)
���������@abeo'
��������
adeo'�@�@�@�`�ɍs��
ineo'�@�@�@����
transeo'�@ ����
pereo'�@�@ �łт�
redeo'�@�@ �A��
�Ȃǂ������ω�������B
�����@�@�@�@�@�@�@�@�ڑ��@
����
eo' imus
eam ea'mus
is itis
ea's eatis
it eunt
eat eant
�ߋ�
i'bam i'ba'mus i'rem
ire'mus
i'ba's i'ba'tis i're's
i're'tis
i'bat i'bant i'ret
i'rent
����
i'bo' i'bimus
i'bis i'bitis
i'bit i'bunt
�@�@�@���X.�^��
�@�@quis�@�@�@�N
quid�@�@�@��
quo'�@�@�@����
cu'r�@�@�@�Ȃ�
�̂ق��Ɂ@�E�E�E�H�i���H�j�ɂ�����
�@�@-ne
no'nne , num
�́A������p���Ď������.
�@�@puellamne amat poe'ta?
���l�������Ă���̂͏����Ȃ̂��H
poe'tane
puellam amat?�@�@�����������Ă���͎̂��l�Ȃ̂��H
�ƌ�����ł���.�܂�
�@�@no'nne�@�́Ano'n + -ne �ŁA�m��̓��������҂��ẮE�E�E�ł͂Ȃ��̂��H������.
�@�@no'nne equo's vide's?
�@�N�ɂ͔n�������Ȃ��̂��H
num �͔��ɁA�ے�̓��������҂��āA���邢�͑z�肵�āA
�@�@num agricolam casti'ga'ba's?
���������N�͔_�v�炵�߂Ă����̂��ˁH�i����Ȃ��Ƃ͂Ȃ��낤�j�B
�@�@�܂��A yes, no �ɂ������͂Ȃ�������ꂽ�����������ĉ���Ɨ�������.
�@�@vide'sne rosa's?
�N�̓o�������Ă��邩�H
�@�@�@�@�@�@�@�@no'n video'.
���Ă��܂���B
�@�@�@�@�@�@�@�@video'.
���Ă��܂��B